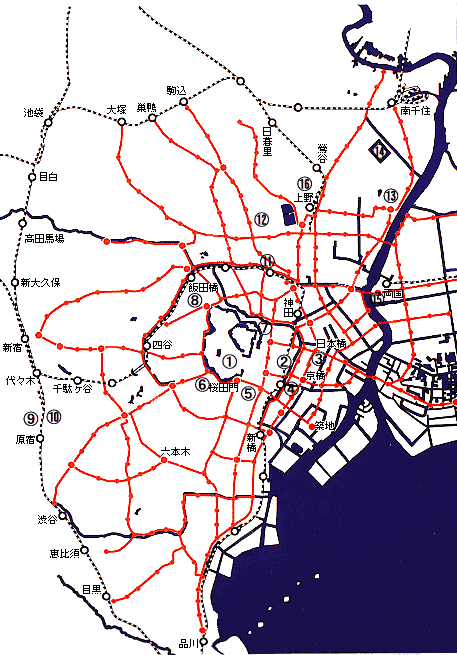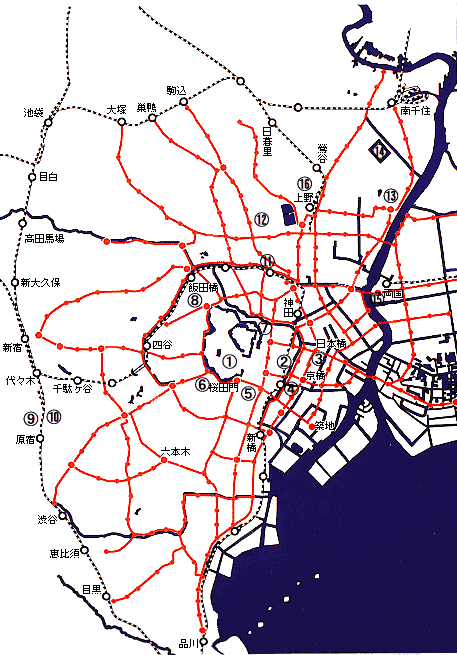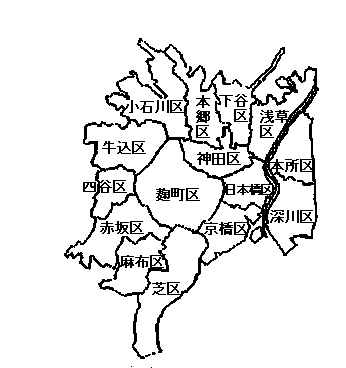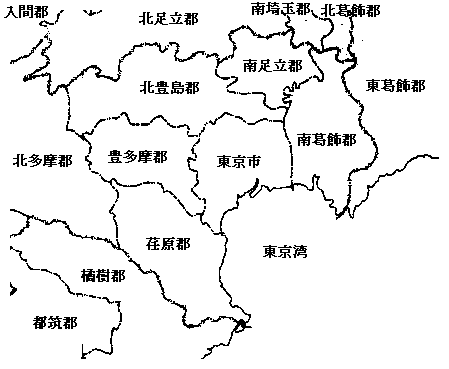帝都の地図、交通
帝都の地図と、鉄道路、そしてそれぞれの土地についての案内です。
■東京市(市内地図)
■東京市行政区地図、東京府地図
■宮城
■東京駅
■日本橋
■銀座
■新橋、築地
■日比谷、桜田門、三宅坂、霞ヶ関など
■馬先門、丸の内、大手町など
■九段
■四谷、市ヶ谷
■万世橋、お茶の水
■本郷、神田、江戸川
■浅草
■吉原
■両国
■上野、上野山
■芝、品川
■帝都の郊外事情
大正期の東京市内の地図地図です。
市内地図では、赤線が市電を、縞線が国鉄を表しています。
※地図がクリッカブルマップとなっていますので、地図をクリックすれば、その項目へと飛びます。
(丸数字ではなく、その地域への説明に飛びます)。
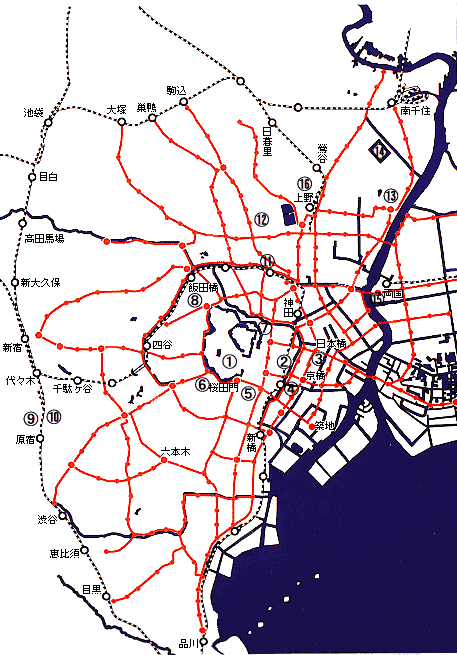
1、宮城 2、東京駅 3、日本橋 4、銀座 5、日比谷公園
6、陸軍参謀本部 7、大蔵省 8、靖国神社 9、明治神宮
10、神宮外苑 11、東京女子高等師範学校 12、東京帝国大学
13、浅草公園 14、新吉原 15、両国国技館 16、上野公園
大正期の東京市15区の区割り地図です。
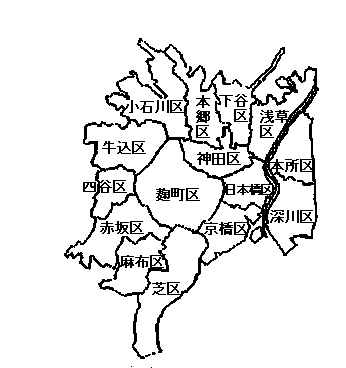
東京市とそのまわりは、下記の地図の様になっています。
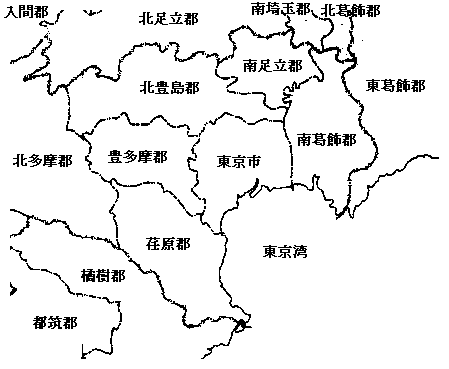
□東京府
東京市、北多摩郡、南多摩郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡、荏原郡
□埼玉県
入間郡、北足立郡、南埼玉郡、北葛飾郡
□千葉県
東葛飾郡
□神奈川県
橘樹郡、都筑郡
※帝都の郊外事情については、こちらを参照してください。
徳川家の居城、江戸城であったものが、明治元年に皇居となり明治21年以来、宮城と称されていました。
皇居前には江戸時代、諸大名の屋敷がおかれていましたが、明治に入るとこれらの屋敷は版籍奉還(明治2年)により
上収されました。一時、明治政府の官衙、兵営等に利用されていましたが、伊藤博文の指示により一切のものが
撤去されるとともに、多くの樹木が植栽され大広場として整備されました。
皇居外苑の南東の一角には、騎馬武者姿の楠正成像があり、この銅像は明治37年7月に完成し献納されたものです
(それにしても天皇家にとって逆賊とも言える楠正成が何故?)。
また、宮城の外堀の千鳥ヶ淵は桜の名所としても有名です。
東京駅は明治41(1908)年から起工し、大正3年に開業しました(その間7年あります)。辰野金吾の設計で、赤煉瓦のネオ・ルネサンス様式の建物です。
これに伴い、新橋駅は汐留貨物駅となり、東海道線の始点を東京駅に譲り、新たに烏森駅が新橋駅となっています。
丸の内側が表玄関の如くで、八重洲口は裏玄関のようでした。
丸の内側の南口が乗車専用口、降車口は北側と決まっており、タクシーの客待ちは北口に限られていました。
市電の停留所も丸の内乗車口、降車口になっていました。
丸の内口には中央口もあり、駅長室や高貴の御休憩室(皇室やVIP用の休憩室)や、さらには専用の昇降場なども用意されていました。
東京駅の開業当初は、広い構内に客も少なく、駅員も少ないという状態でした。また、まわりには丸ビルをはじめとした
高いビルがまだなく、堀端からその偉容が丸見えという状態でした。
日本橋川に架かる日本橋は、慶長8年(1603)年に架けられ、その翌年にはここを起点に里程が
定められました(現在でも、「日本国道路原標」の円形レリーフがはめ込まれ、0キロスポットとなっています)。
明治44年(1911)年に現在の長さ27間、幅15間のルネサンス式の石造橋となっています。
日本橋は橋そのものの意味に止まらず、橋を中心にした地域の名称であり(日本橋区です)、金融面では、
近くに日本銀行を始め諸銀行の本店、証券取引所などを控え、また商業面では、問屋、百貨店、魚河岸などがありました
(これらの魚河岸は関東大震災後に築地に移動します)。
文化面でも博文館、金港堂、春陽堂、大倉書店などの大手出版社や、洋書輸入の丸善などが点在していました。
また、白木屋百貨店(現在の東急)、高島屋など有名百貨店が集まっており、中でも東洋一と謳われ、
「今日は帝劇、明日は三越」のコピーで一斉を風靡した三越呉服店(昭和3(1928)年に「三越」になりました)の人気は全国的に高かったようです。
三越呉服店は明治41年に洋風ルネサンス式3階建てで始まり、増改築を重ねて巨大化しました。
当時は大百貨店は全国的に少なく、百貨店そのものが名所として多くの人々が市電に乗って訪れていました。
銀座は、近くに築地居留地が慶応3(1867)年から、明治32(1899)年まであったために、
文明開化の波が直撃する地域でした。
明治5(1872)年の大火により焼失した銀座を、明治政府はいち早く煉瓦街を建設すると宣言、焼け出された
住民や、焼け残った住民などを無視して、強引に建設を押し進めました。
様々な問題はありましたが、不燃都市化計画の第一号は、明治7年に煉瓦街の新橋−京橋のメインストリート(一等家屋)
が完成しました。
その後、二等、三等家屋も竣工されましたが、一等家屋ですら不人気でなかなか住民が集まりまらずゴーストタウンの様でしたが、
政府側の強硬な姿勢が解けるに従い、徐々に住民が増え、明治15年頃には西洋的な繁華街へと変貌しました。
また、車道と歩道の区別が最初につけられ、松と桜、柳が植えら、並木道が造られました。
明治末期には路面電車がメインストリートである銀座通りに開通しています。
また、明治末期から大正初期には様々な観工場(小さなデパートの様なものです)、ビアホール、カフェなどが次々とでき、
モダンな町並みへと変化していったのでした。
中でも有名なのは、服部時計店(現在の服部セイコー)の時計塔(明治28年建設)や、カフェ・ライオンカフェ・プランタン、カフェ・パウリスタ(3つとも明治44年開店!)、
そして初のビアホールである恵比寿ビヤホールなどです。
また、大正初期の頃から「銀ブラ」と言う、銀座をぶらぶら散策、散歩するという言葉が一般に使われ始めました。
築地には鉄砲洲(築地)居留地が開かれており、外国人に便宜を図るため、ホテル(特に有名だったのが築地ホテル館です)、
遊郭、電信局(築地−横浜間)がありした。
当初、横浜よりも商取引に不便なため、進出する外国人も少なく、遊郭も明治4年に閉鎖、ホテルは5年の
大火で焼失しました。
その後、洋館が建ち始め、アメリカ公使館、立教学院(後の立教大学)、東京三一神学校などが建設されました。
また、明治5年に建設された新橋駅は日本で始めての本格的な駅であり、当初は東海道線の始発駅でした(大正3(1914)年に東京駅が始発駅となり、
新橋駅は汐留貨物駅となりました)。同年には新橋−横浜間(50分程度かかった様です)が全通して
蒸気車が始めて運転されました。
新橋付近にも、千疋屋果物店(現在の千疋屋)や、青柳菓子店(現在の青柳?)、萬屋洋傘屋、木田金盛書店、大徳帽子店など
様々な商店が存在していました。
また、福地桜痴の発案によって建てられた初代歌舞伎座は洋風でしたが、明治44年に改築されたものは、同年に建築された帝国劇場に対し、
日本式の宮殿づくりとなっていました。
そして、さらに大正10年に火事で焼失、大正13年に復興した歌舞伎座は鉄筋コンクリート建築の桃山風でした。
また新橋は、「新橋芸者」で有名でした。明治政府の高官達によって利用された花柳会街で、柳橋と帝都の
華を競いました。
築地居留地が閉鎖された後、鏑木清方の名画で有名な明石町となり(メトロポール・ホテルは明治38年に開業、同42年に閉業しました)、
さらに震災後、築地は日本橋におかれていた魚市場が中央卸売市場がおかれることになり、外国人居留地であった頃の異国情緒を全く失いました。
日比谷公園はそれまでの日本庭園式の公園ではなく、外国人が散歩したり憩える西洋式の公園を作ろうと、
明治政府の西欧化思想の一環として設計され、明治36年に公園の中に噴水や、花壇、音楽堂のなどの設備が
整えた西洋式の公園として開かれました。
江戸城を巡る濠には36見附があったといいますが、明治維新後ほとんどが桝形を解かれるか、あるいは
櫓や門そのものが取り壊されていますが、中には残ったものがあります。
江戸城西南の桜田門で、かつては小田原門と呼ばれた重要な門の一つでした。
この日比谷、桜田門、霞ヶ関、三宅坂などの外堀の廻りには大正期は様々なビルヂング(笑)が連なっており、
有名なものだけでも、陸軍参謀省、海軍省、司法省などの各省、警視庁、東京控訴院、帝国劇場、帝国ホテルなどがありました。また、
鹿鳴館は帝国ホテルの隣にありました。
また、虎ノ門方面では、東京女子学館や、華族女子大学があります。
最初の帝国ホテルは、渡辺譲の設計で木骨煉瓦造りのネオ・ルネサンス様式で、明治23年に完成、客室が92室、
取締会長が渋沢栄一で営業を開始しました。
主に外国人のための宿泊施設でしたが、先端的な社交場でもありました。
二代目の帝国ホテルは、フランク・ロイド・ライトの設計で大正11年の完成です。
帝劇の愛称で呼ばれた帝国劇場は、明治44年に完成し、パリのオペラ座を模した本格的洋風劇場で、一流の劇、音楽会で
上流階級を魅了しました。
三宅坂は帝国陸軍参謀本部(参謀省)の代名詞ともなっており、参謀本部の建物はカペレッチー設計の瀟洒な
白亜の殿堂となっていました。
馬先門、丸の内、大手町はビジネス街であり、日比谷方面から続く官庁街で、東京商業会議所(東商ビル)、
明治生命ビル、東京府庁、丸の内ビルヂング、三菱銀行、三菱本社、東京中央郵便局、電話本局、逓信省、
商工省、農林省などのビルが集中していました。
馬先門の両側には赤煉瓦の西洋風の近代建築が立ち並び、「一丁ロンドン」と呼ばれました。この、
「一丁ロンドン」と呼ばれた丸の内一帯は政府の都市計画に基づいて、岩崎弥太郎(三菱グループの総帥)が
1坪あたり5円という破格の安値で入手した地域でした。
これらの丸の内、大手町に林立するビルは日本の資本主義の牙城であり、サラリーマンが闊歩していた歴史を秘めています。
大手町には大蔵省があり、大蔵省の裏には神田明神の御手洗池がありました。
池の中には千鳥岩と云われる岩があり、その岩のそばには井戸があります。その井戸で、平将門の首が
洗われたのです。また、首は池の側の塚に葬られていると云われています。
神田明神は平将門を祀った社ですが、将門の首は大蔵省裏の首塚に葬られているのです。
九段は昔は麹町台地に上るための急峻な難所で、石段が取り払われた後も難所であることに変わりなく、
最初は九段坂の下と、上で電車が折り返していました。
明治43年に九段坂の南側に都電専用の軌道が作られ、千鳥が淵沿いに電車が通るようになっています。
春になると桜の枝先が車窓をなでて、電車から花見としゃれ込んだと云われています。
この九段坂の上には近衛一連隊、二連隊があり、坂の途中には払い下げの靴や、参謀本部の測量図、
地図入りケース、水筒などを売る店が並んでいました。
また、坂上には靖国神社もあり、春秋の二度の大祭には都電も通れないほどの人でごった返しました。
市ヶ谷には明治11年に新学校が竣工した陸軍士官学校がありました。
士官学校の卒業までの期間は3年で、大正9年には陸軍中央幼等学校を合併し、本科、予科の制度設けられています。
太平洋戦争中には大本営陸軍部が設置されたり、戦後は極東国際軍事裁判所の法廷が開かれ、その後に自衛隊市ヶ谷駐屯地と
なっています。そして、昭和45年、三島由紀夫が割腹自殺を遂げた場所でもあります。
迎賓館は旧紀州藩徳川邸で、明治5年に赤坂離宮となりましたが、手狭な和風建築のため、明治32年から10年かけて
フランスのベルサイユ宮殿風の耐震構造建築が建てられました。
内部の旭の間、花鳥の間、羽衣の間など豪華な室内装飾には当時の一流の画家が多数動員されています。
明治天皇ゆかりの明治神宮は大正9年に完成、青山練兵場跡には、大正10年に聖徳記念絵画館が、大正15年には
神宮球場が完成し、帝都のレクリエーションの土地としてにぎわっていました。
万世橋は東京駅完成前までは最も繁華な、「都会の親不知」と云われたほどの繁華の地でした。
万世橋駅は赤煉瓦づくりの東京駅を思わせる建物で、元々は甲武鉄道株式会社の始発駅としての構想をもとに
作られ、駅内には乗車券発売窓口や各等待合室、食道などを備えたターミナル駅であり、明治45年に開業しました。
しかし、完成前に鉄道国有法が施行され、甲武鉄道は国有化されました。東京駅と万世橋駅が電車専用複線で
繋がったのは大正8年のことです。
万世橋を有名にしたのは、日露戦争で旅順港封鎖で、我が艦と運命を共にした広瀬中佐と杉野兵曹長の背の高い
銅像でした。
万世橋の付近には神田川に沿った柳原の古着街や、西南に多町一帯には神田青果市場があったため、水菓子商が多く、
馬車や大八車でごった返していました。
またこの青果市場は日本一の規模で、「ヤッチャ場」の愛称持ち、威勢のいい兄いが忙しく働いていました。
明治、大正期のお茶の水界隈は聖橋やニコライ堂などを臨み、風水勝絶と云われ、緑豊かで水清く閑静な土地だったためか、順天堂、杏林堂、井上眼科、
瀬川小児科、濱田産科、高木耳鼻科などの高名な病院が多くできていました。
また、東京女子高等師範学校があり、その敷地内には付属の幼稚園、小学校、女学校がありました。
東京女子高等師範学校は、震災後は小石川区大塚に移転しました(戦後、大学になったときに、お茶の水女子大学となります)。
その昔、「本郷もかねやすまでは江戸の内」と川柳に歌われ、「かねやす」というのは江戸初期から続く
小間物屋です。本郷追分は日本橋からちょうど一里の付近で、戦前までは一里を示す碑が建っていました。
本郷の東京大学は明治10年に創立(明治19年に帝国大学、いわゆる帝大となっています)されており、
そのためか明治10年代には日本橋や芝に多かった古書店が神田に集まって来たのは明治20年代で、
小川町や神保町などが発展したのは30年代だと云われています。
夏目漱石の「三四郎」に登場する銀杏並木は赤門とともに帝大の象徴となっています。
安田財閥の寄付をもとにした安田講堂が初めて卒業式に使用されたのは、昭和2年の事で、この講堂の
南側には、「三四郎池」と呼ばれる心字の池の庭園があり、加賀前田家の屋敷の面影を良く残しています。
銀杏の葉が散る頃には、黒マントを纏った学生が構内を闊歩していました。
湯島天神は本郷台の東端にあり、天之手力男之命と、菅原道真を祀っています。明治には公園に指定され、
梅や楓が多く、初日の出、月見の名所として知られました。また、管公に関わり深い梅の名所でもあります。
湯島天神からほど近い場所に神田明神があります。神田明神は最初将門塚の周辺に建っていたのですが、
江戸初期に徳川家康が現在の位置に移したと云われています。
神田明神は江戸の江戸総鎮守として江戸の庶民にも親しまれてきました。
神田上水の一部で小石川関口台付近から飯田橋までを「江戸川」と呼びました。
この江戸川橋から駒塚橋までの川沿いには、大正8年に江戸川公園が出来て、崖地と水路を利用した散策路が
設けられていました。
江戸川の周辺は明治期には「新小金井」と呼ばれる花見の名所で、往事は船宿が数十軒もあり、船を借りて
宴会や夜桜を楽しんだと云われています。
浅草は江戸期以来東都名所の筆頭で、浅草寺の門前町です。
雷門は風神雷神門の略称で、左右にこれら二つの像がありましたが、慶応元(1865)年に火事で焼け落ち、
以来昭和35(1960)年に再建されるまで、実に95年もの間、門はありませんでした。
浅草寺の縁起は、「推古天皇三十六(628)年三月十八日の朝まだき、郷族桧熊浜成・竹成の兄弟、江戸浦(隅田川)に漁撈中、
はしなくも一身体の御尊像を感得す」と云われ、この引き上げられた観音像にお堂を建てて供養したのが浅草寺の創始だといわれています。
下町庶民のみならず東京市民から全国から集まり人々、さらには外国人まであつめて繁盛しています。
観音堂の隣の浅草神社の三社祭、四万六千日のほおずき市、植木市、羽子板市などの祭や市には、たくさんの人が繰り出します。
明治6年に浅草寺の境内が公園に指定され、続いて同17年に7区に分割され(7区(浅草馬道周辺)はその後除外された為、6区と呼ばれます)、五区の奥山には動物園や植物園を兼ねた花屋敷が繁盛し、
大正期にはメリーゴーラウンドが人気でした。
六区には、見世物小屋、劇場、映画館が集中した興行で、金竜館(オペラ)、常磐座(演劇)、東京倶楽部(活動写真)などが
ありこの三館は共通入場券でした。
仲見世一帯は浅草寺の寺内で、明治元年に東西両側に赤煉瓦造りで棟割り店舗を作って貸し出しました。
東西で何十軒の生業は、この繁華な土地で廃れることはなく、今日でもそのほとんどは開業以来の店となっています。
中には現在でも有名な雷おこしの常盤家の常磐楼料理店や、共栄勧業場がありました。
また、浅草のランドマークタワーとして有名な凌雲閣は通称十二階と言い、明治23年に完成し、設計はウィリアム・バートンで、
八角形の赤煉瓦造りで、高さは220尺(66m)にも及んだと云われています。十二階の真ん中にエレベーター、
まわりに螺旋階段でも登れるというもので、これに登れば関東一円を眺めることが出来ました。
十二階は関東大震災の時に、8階から折れて倒壊しました。
凌雲閣の前には、有名な瓢箪池もありました。
吉原は江戸時代より御免色里(つまり、幕府公認の遊里)として有名でした。
日本橋人形町の辺りに最初の吉原はありましたが、明暦の大火(いわゆる振り袖火事)により、吉原は類焼し、さらに幕府からの命もあり、
そのまま浅草山谷に引っ越すことになります(この日本橋にあった吉原が「元吉原」、浅草の吉原を「新吉原」と呼びますが、
浅草の吉原を単に「吉原」と呼んだようです)。
幕末には一時的に衰退しましたが、明治2年には早くもその賑わいを取り戻し、五勢楼、金瓶大黒、佐野槌など
洋風建築が続々と建てられ、明治末期にはいち早く電気が使用されていました。
吉原は約3万坪の広大な土地に建てられ、周囲はおはぐろどぶと呼ばれる濠で囲まれています。
このおはぐろどぶは、大正期には3尺(約1m)程度しか残っていませんでしたが、江戸期には5間(約9m)あったと言われています。
吉原は大門より入ったメインストリートを仲之町を中心として、左右に大きな通りが横切っています。
手前から右側が江戸一丁目、左側が江戸二丁目、次ぎが右が揚屋町、左が角町、そして一番奥の右が京町一丁目、
左が京町二丁目となっています。また、これらの横切る大きな通りの左右には非常門が設置されており、
火災などの際は、客がそこから避難することができました(花魁などの吉原の人間は、まず門に設置されている
番屋で外出許可を取ったり、あるいは鑑札を見せなければ、外に出ることができません)。
吉原を取り仕切っていたのは、花魁のいる貸座敷を取り仕切る新吉原貸座敷組合、引手茶屋を取り仕切る
新吉原引手茶屋組合、芸者を取り仕切る新吉原芸妓組合で、そしてさらにその3つの組織を取り仕切っていたのが
新吉原三業取締事務所で、これは仲之町奥にある水道尻にありました。
千葉への街道を東に行けば、両国橋を渡る前から見えたのが両国国技館でした。
江戸時代から相撲は一月と五月を例として、国技館の隣の回向院の境内で行われていました。そのころは、
晴天十日間で、雨の日は日延べをしなければなりませんでした。
しかし、この両国国技館が完成してからは日延べも無くなりました。
両国国技館は、明治39年着工、同42年の春場所から相撲が行われるようになりました。鉄筋コンクリートの4階建てで、
一万六千人を収容できたと云います。またの名を大鉄傘と言い、全国的に帝都の名所でした。
両国国技館はその後大正6年に焼失し、同8年に再建、さらに関東大震災でもう一度焼失、そして同13年に
再建竣工されました。
両国には明治37年に総武鉄道会社線の始発駅として両国橋駅ができ、昭和6年に両国駅となりました。
また江戸、明治、大正期の両国橋西側の広小路は繁華街として知られ、勧業場、落語席があり、
売薬商や様々な商店が建ち並んでいました。
上野は寛永2(1625)年に怪僧天海の進言により、幕府の祈祷寺として天台宗の東叡山寛永寺を開きました。
寛文年間より、江戸の花見の名所として有名で、また山を降りると上野の町は実に庶民的で、江戸でも有数の盛り場が成立しました。
上野は明治元年の彰義隊の戦いでほとんど焼け野原となり、その後、明治6年の太政官布告を受けて、
いち早く公園として整備され、明治11年の国立博物館を筆頭に、良家の子弟教育を目的とした帝国学士院、
動物園、東京図書館、東京美術学校、東京音楽学校などが次々に建設され、文化の殿堂としての上野となりました。
また、上野は繁華街としての歴史も長く、「聖」と「俗」が隣接する活気に満ちた街です。
その中核であった松坂屋(当時は「松坂屋いとう呉服店」)は、明治40年に上野店をゴシック調の洋風建築の
正面に円形二層の塔屋を持った四階建てのビルに一新しており、これに伴い呉服屋から勧業場、デパートへと移行しました。
江戸期より不忍池は蓮の名所として、上野山は桜の名所として有名です。
「桜の下には死体が埋まっている」とは、誰が云い始めたかは知りませんが、上野の山と云えば彰義隊事件に
関東大震災で死体が山と積まれた場所です。
一説には上野に立っている西郷隆盛像は、彰義隊の怨霊を封じるために明治政府が置いた要石の様なものだとも
云われています。
芝から品川にかけては街道筋にあたり、人々が忙しく行き交う地域でした。
愛宕神社、寛永三馬術、放送局で有名な愛宕山、徳川家の霊廟を持つ増上寺、その境内の一部を公園とした
芝公園、東海道を江戸に入る人馬荷物を検査した高輪大木戸、四十七士の墓がある泉岳寺あどがあります。
また、品川宿は、明和3(1766)年以降、飯盛女五百人に限って置く事が許されて以来、品川遊郭と
して発展しました
鉄道の駅が品川の海岸近くに建設されたのは明治5年で、以降ターミナル駅として機能し、上野浅草行きの
市電、六郷土手行きの京浜電車の起点となりました。
関東大震災後は、海岸沿いの埋立地は電機、機械工業を中心とした工業地区として発展し、西側の台地は
住宅地となりました。
大正期の帝都の住宅事情は非常に厳しいものとなっています(一部の華族や、成金たちが大邸宅を競って
建てていましたが)。
大正10年前後で帝都郊外にかなりの家屋が建ち、市内での住宅難も緩和されるかと思われましたが、
事実は正反対であり、市内ではますます住宅の底払いを来たし、家賃などもだんだんと値上げされる傾向にありました。
なぜなら、期待された郊外、郡部へと引っ越していった者達が、いざ住み暮らしてみると道が悪いうえに、
交通機関が不便のため、日用品の需給も滞りが発生しており、そのため却って市内よりも物価が高いという
現象が起こっており、さらに郊外では一部で警察力が薄く治安が悪く、殺人強盗窃盗などの犯罪が多いため
再び市内へと逆戻りするためです。
郊外、特に西巣鴨、池袋、滝野川の辺りがもっとも甚だしく新築の貸家が半分も空いたままで貸し手が
つかないでいるという有様で、中には家賃100円と切り出した家を75円、68円と切り下げていき、
最後には45円にもなってしまったという実例もあり、現在住民がいる家でも1割、2割の値下げがされているのが
普通です。
目黒、中野、大井、大森、品川の辺りでも同様の現象が発生していますが、何しろ市内に空き家が少ないために
市内に帰ることができず、そのまま不便を忍んでいる事もままあります。